FNCA2008���ː����S�E�p�����Ǘ��iRS&RWM�j���[�N�V���b�v
�T�v
11��3�|7���A�I�[�X�g�����A�E�V�h�j�[
�@2008�N�x��FNCA���ː����S�E�p�����Ǘ����[�N�V���b�v�́A����20�N11��3������7���܂ł�5���ԁA�����o�[��13���̐��Ƃ��Q�����A�I�[�X�g�����A�̃V�h�j�[�ɂ����ĕ����Ȋw�Ȃƒn����Ñg�D�Ƃ��ẴI�[�X�g�����A���q�͉Ȋw�Z�p�@�\�iANSTO�j�Ƃ̋��ÂŊJ�Â���܂����B
|

|
������4�ԖځF�����Á@�q�����i���{�v���W�F�N�g���[�_�[�j
�E����4�ԖځF�����E�L�����������i���R�[�f�B�l�[�^�[�j
�E����3�ԖځF���r�E�f�B�~�g���t�X�L���i���v���W�F�N�g���[�_�[�j |
1�j���[�N�V���b�v�̊T�v
 |
Ron Cameron���iANSTO�j
�I�[�X�g�����A �R�[�f�B�l�[�^�[ |
 |
�������i����j
���{�v���W�F�N�g���[�_�[ |
�@�{�v���W�F�N�g�́AFNCA�Q�����Ԃɂ����ĕ��ː����S����ѕ��ː��p�����Ǘ��Ɋւ������o���ɂ�蓾��ꂽ�m�������������L���邱�Ƃɂ��A�A�W�A�n��ɂ�������ː����S����ː��p�����Ǘ��̈��S���̌���Ɏ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ����v���W�F�N�g�ł��B����7�N�i1995�N�j������{���Ă������ː��p�����Ǘ��v���W�F�N�g�����g���āA�V���ɕ���20�N�i2008�N�j�ɊJ�n���܂����B�v���W�F�N�g�����̒��S�́A�N1��e���������ŊJ�Â��郏�[�N�V���b�v�ŁA�e���̃v���W�F�N�g���[�_�[���邢�̓��[�N�V���b�v�ɂ����铢�c�e�[�}�ɑ��������Ƃ����ق��ĊJ�Â��܂��B
�@
�@����́A�v���W�F�N�g�̃e�[�}����ː��p�����Ǘ�������ː����S�E�p�����Ǘ��Ƃ��炽�߂čŏ��̃��[�N�V���b�v�ł����BFNCA�Q��8�����A���Ȃ킿�I�[�X�g�����A�A�o���O���f�V���A�����A�C���h�l�V�A�A���{�A�}���[�V�A�A�^�C����уx�g�i��������ː����S���邢�͕��ː��p�����Ǘ��Ɋ֘A���鐭��A�K���A���Ƃ���ь����J�����Ɍg����\��13�����Q�����A�J���g���[���|�[�g�̔��\�A����̃e�[�}��ݒ肵���T�u�~�[�e�B���O����щ~�쓢�c���s���A�����ANSTO�̎{�݂ւ̃e�N�j�J���r�W�b�g�����{����܂����B
2�j�J�ÊT�v
| ��j |
�����F |
����20�N11��3���i���j�`7���i���j |
| ���j |
�ꏊ�F |
�I�[�X�g�����A�@�V�h�j�[ |
| ��j |
��ÁF |
�����Ȋw�ȁA�I�[�X�g�����A���q�͉Ȋw�Z�p�@�\�iANSTO�j |
| ��j |
�Q���ҁF |
�I�[�X�g�����A2���A�o���O���f�V��1���A����1���A�C���h�l�V�A1���A���{4���A�}���[�V�A1���A�^�C2���A�x�g�i��1���A���v13���i�Y�t�����Q�Ɓj |
| ��j |
�����F |
�Y�t�����Q�� |
�@���[�N�V���b�v��1���ڂ́A�Z�b�V����1�Ƃ��āAFNCA�e��������ː����S�ƕ��ː��p�����Ǘ��̌���Ɛi���ɂ��ẴJ���g���[���|�[�g�����\����A���̌�AFNCA�Q�����̂���Ȃ闝�𑣐i�̂��߂ɃI�[�X�g�����A�Ɠ��{���ޗ�����A�|�X�^�[�Z�b�V�������s���܂����B
 |
![�|�X�^�[�Z�b�V�����̗l�q�@�ߍ]���i���d�j](workshop2008_img/05.jpg) |
�Z�b�V����1�̗l�q
�����Î��ɂ����� |
�|�X�^�[�Z�b�V�����̗l�q
�ߍ]���i���d�j |
| ���ː����S�̊�{�ɂ��ď����Î����T�����A�����ŃZ�b�V����2�Ƃ��ĎQ���e������J���g���[���|�[�g�����\����܂����B |
���{�̌��q�͔��d���ɂ�������ː��h��̎���̏Љ� |
 |
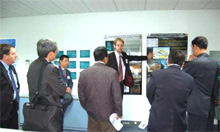 |
�|�X�^�[�Z�b�V�����̗l�q
�������i�d�����j |
�|�X�^�[�Z�b�V�����̗l�q
Dancan���iANSTO�j |
| ���ː��̑���Ƒ����̎��ۂɂ��Ă����2010�N�ɓ��{�ł̊J�Â��\�肳��Ă���AOCRP3�̗\�蓙���Љ��܂����B |
ANSTO�ɂ�������ː��p������g���s���������̃��X�N�ƃZ�L�����e�B�̊ϓ_����̎�舵���̎��Ⴈ���OPAL�����F�̎��^�]�̏����Љ��܂����B |
�@2���ڂɂ́A�Z�b�V����3�Ƃ��ăJ���g���[���|�[�g����̓��ʃg�s�b�N�X�i���ː��h��ƕ��ː��p�����Ǘ��j�A����уZ�b�V����4�e�[�}1�Ƃ��āu���ː��p�����{�݂̃T�C�e�B���O�v�ɂ��āA�e�[�}2�Ƃ��āu�Q�����ɂ�������S�Ɋւ��鏔���v�����\����c�_���s���܂����B
�@�Z�b�V����3�ł́A���ׂĂ̏o�ȍ����甭�\������܂����B�I�[�X�g�����A�����ANSTO�ɂ����鏜���̎���A�o���O���f�V������͔p���������ƒ����̂��߂̏W�������{�݂̐ݒu�ɂ��āA��������͕��ː���Ə]���҂̃��j�^�����O���ʓ��A�C���h�l�V�A����͐��ʍS���l�Ɣr�o���x�ɂ��āA���{����͌��q�͔��d���ɂ�����l���ʌv�ɂ��āA�}���[�V�A����͕��ː���Ə]���҂̐��ʕ��z�A�^�C����͕��ː�����̏A�x�g�i������ً͋}�����r���[�̑Ή��ɂ��Ă��ꂼ��Љ��܂����B�Z�b�V����4�̃e�[�}1�ł́A�I�[�X�g�����A����k�����B�iNorthern Territory�j�ɐݒu����邱�ƂɂȂ������ː��p���������T�C�g�ɂ��āA�o���O���f�V��������ː��p���������{�݂̑��ƑO�̈��S���Ɋւ���Љ����A�e�[�}2�ł́A�^�C����R�o���g60�����ɂ��[���Ȏ��̂̏Љ����A���{����ALARA�̊T�O�Ƃ��̈�ʌ��O�ւ̓K�p�ɏœ_�����Ă�������s���܂����B
 |
 |
| Udorn���iTINT�j��Dancan���iANSTO�j |
Syahrir���iBATAN�j��
L. Dimitrovski���iANSTO�j |
 |
 |
M. Islam���iBAEC�j��
K. Fernando���iANSTO�j |
|
�@3���ڂ́AANSTO�̎{�݂ւ̃e�N�j�J���r�W�b�g���s���܂����B���ƃf�R�~�b�V���j���O���s���Ă���MOATA�����HIFAR�F�̌��w�ƕ��ː��p�����Ǘ��̌����Ɋւ��郌�r���[���s���A��x�����ː��p�����̒��Ԓ��������w���Ă��̈��S�����c�_���A�܂��������ː���ł̍�Ƃ��s���z�b�g�Z���̗��p�ɂ��Ċm�F���܂����B�܂��A�V�^��OPAL�F����K�₵�A�����ANSTO�̕��ː��p�����̃N���A�����X�V�X�e���A���ː��p���������̍�Ƃ̏ɂ��Č��w���܂����B
 |
 |
| ��x�����ː��p�����h������ |
�h�����ʂ̒����̗l�q |
| 4�i�ς݂ɂȂ��Ă���B�����̌����́A�قږ��t�ł��邽�߁A�V���Ȍ����̌��݂��������ł���B |
4�i�ς݂ɂȂ��Ă���B�����̌����́A�قږ��t�ł��邽�߁A�V���Ȍ����̌��݂��������ł���B |
 |
 |
| HIFAR �F�̏㕔 |
HIFAR �g�p�ςݔR���̂��߂̈ړ����u |
| HIFAR�F�ɂ�280g�̃E�������܂�25�̔R���v�f���}�������悤�ɂȂ��Ă���B |
HIFAR�F�ł́A��L�̌`��̓��ʎd�l�̈ړ����u��p���āA4�T�Ԃ��ƂɁA3���邢��4�̔R���v�f���F������o����A�אڂ��钙���v�[���Ɏ��[���ꂽ�B |
 |
ARPANSA�̋K���Ɋւ������
S. Sarkar���iARPANSA�j |
�@4���ڂ́A�Z�b�V����5�Ƃ��āu���q�͔��d������ь����F�ɂ�������ː����S�v�Ƒ肷��T�u�~�[�e�B���O���s���܂����B���{����u���q�͔��d���ɂ�������ː��h��V�X�e���v�A�܂��I�[�X�g�����A�̋K����S������ARPANSA�̋K��������uANSTO�̌��q�͎{�݂̈��S�Ǘ��Ɋւ���ARPANSA�̕]���v�A����Ƀ}���[�V�A����u�}���[�V�A�̈�Õ��ː��p�����̊Ǘ��ɂ�������S���v�Ƒ肷��v���[���e�[�V����������A���ꂼ�ꎿ�^�������s���܂����B
 |
| J. Easey���iANSTO�j |
�@���̌�A�Z�b�V����6�Ƃ��āuIAEA/ANSN�ARCA/RAS9042���̑��̍��ۋ��̓v���O�����Ƃ̒����v�Ƒ肷��~�쓢�c���s���܂����B�~�쓢�c�ł́A�Q���e�����炻�ꂼ��̌o����ӌ����Љ��A����A���̍��ۋ��̓v���O�����Ƃ̒������s���L���Ȋ�����W�J���Ă������Ƃ��m�F����܂����B
�@ANSTO�ɂ����Ē��N�ɂ킽�荑�ۋ��͊����Ɍg����Ă���Dr. John Easey����FNCA�̂���܂ł̊����Ɋւ���^�Ǝӈӂ�\������ƂƂ��ɍ���̊����ւ̊��҂��q�ׂ��܂����B
 |
| �����Î��ɂ��܂Ƃ߂̗l�q |
�@�Ō�̂܂Ƃ߂ł́A�����Î����uFNCA���ː����S�E�p�����Ǘ��v���W�F�N�g�̊����Ə����ɂ��āv����������A�܂�����̊����̓W�J�ɂ��Ď��グ��ׂ��g�s�b�N�X�Ă�������A�e���̊�]��ӌ����W���ʓI�Ȋ�����i�߂Ă������Ƃ��m�F����܂����B���[�N�V���b�v�̍Ō�ɁA���v���W�F�N�g�͊e���ɑ��ėL�v�Ȓm���Ə��������炵�A���ː����S�ƕ��ː��p�����Ǘ��̗����A���ɋZ�p�I���ʂɊւ��闝���̑��i�Ɍq����A�A�W�A�����ɂ�����������𑣐i���邱�Ƃ����҂���邱�Ƃɂ��č��ӂ��܂����B
|